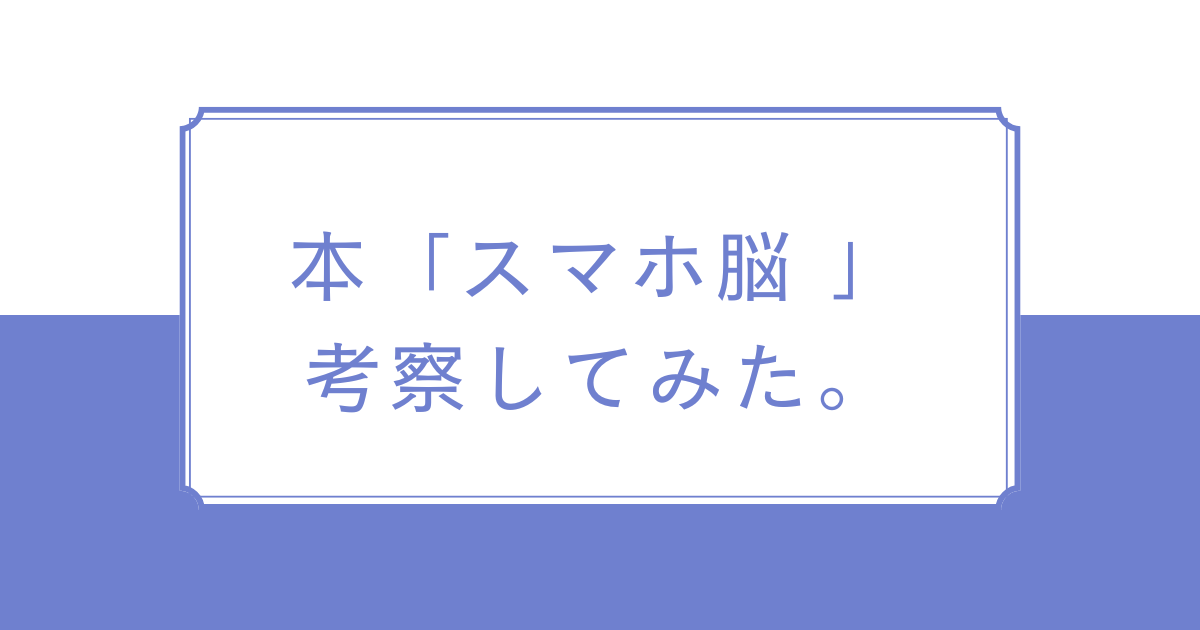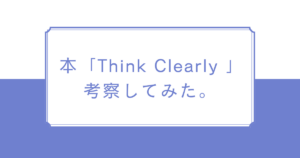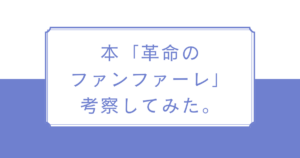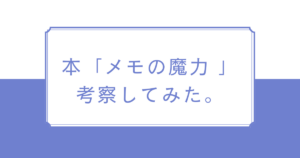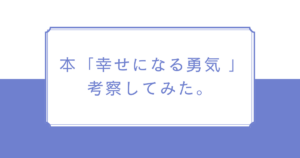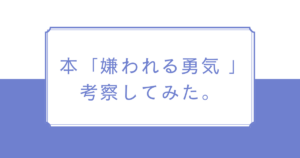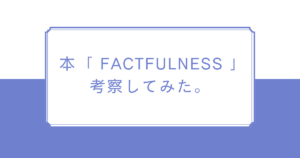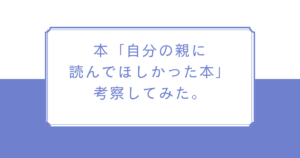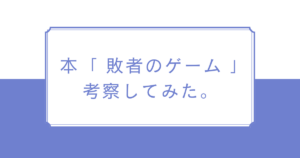「スマホ脳」は、アンデシュ・ハンセン氏によるベストセラーで、スマートフォンが私たちの脳に与える影響を科学的に解説した一冊です。
現代社会において、スマホは生活に欠かせないツールとなっていますが、その使い方によっては脳に深刻な影響を及ぼす可能性があります。
今回は、本書の核心を考察し、スマホが私たちの生活にどのような影響を与えているかを探ります。
考察① スマホが脳をハッキングするメカニズム
スマホが私たちの脳に与える最大の影響は、ドーパミンという神経伝達物質の過剰な放出です。
ドーパミンは、報酬や快感を感じた時に分泌される物質で、新しい情報や「もしかしたら」という期待感によって活性化されます。
スマホは、このドーパミンを巧みに利用して、私たちの脳をハッキングしているのです。
例えば、SNSの通知やゲームのガチャシステムは、ランダム性や期待感を利用してドーパミンを放出させます。
新しい情報が飛び込んでくるたびに、私たちは「次は何が来るか」と期待し、スマホを触り続けてしまいます。
このような仕組みによって、スマホは私たちの注意力を奪い、依存を引き起こすのです。
考察② スマホ依存がもたらす弊害
スマホ依存は、私たちの生活にさまざまな弊害をもたらします。
まず、集中力の低下が挙げられます。
人間の脳は、マルチタスクに適応しておらず、一度に一つのことしか集中できません。
スマホを触りながら他の作業をすると、情報が脳の適切な場所に保存されず、記憶が曖昧になったり、物忘れが増えたりします。
次に、睡眠不足も深刻な問題です。
スマホから発せられるブルーライトは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を抑制します。
寝る前にスマホを触ることで、体内時計が乱れ、質の良い睡眠が取れなくなります。
睡眠は脳の老廃物を除去し、記憶を整理する重要な役割を担っているため、その不足は脳の機能に直接的な悪影響を及ぼします。
さらに、子供の脳への影響も無視できません。
脳の前頭葉は、衝動をコントロールする役割を担っていますが、完全に発達するのは25歳から30歳頃です。
子供の頃からスマホに触れすぎると、依存症になりやすく、集中力や記憶力の低下を招くリスクが高まります。
考察③ スマホ依存への対抗策
スマホ依存から脱却するためには、いくつかの具体的な対策が有効です。
まず、スマホの使用時間を制限することが重要です。
iPhoneの「スクリーンタイム」機能などを活用し、自分がどれだけスマホを使っているかを把握しましょう。
プッシュ通知をオフにしたり、SNSの利用時間を決めるだけでも、スマホに費やす時間を減らすことができます。
次に、運動を取り入れることも効果的です。
運動は、集中力を高め、ストレスを軽減する効果があります。
散歩やヨガ、ランニングなど、自分に合った運動を習慣化することで、スマホ依存から抜け出す手助けになります。
最後に、SNSデトックスもおすすめです。
SNSは他人との比較を生み、自己評価を低下させる原因となることがあります。
積極的に交流したい人だけをフォローし、SNSを「つながりの道具」として捉え直すことで、精神的な負担を軽減できます。
まとめ
「スマホ脳」は、スマホが私たちの脳に与える影響を科学的に解き明かし、その危険性を警告しています。
ドーパミンを利用したスマホの仕組みは、私たちの注意力を奪い、依存を引き起こします。
集中力の低下や睡眠不足、子供の脳への悪影響など、スマホ依存がもたらす弊害は深刻です。
しかし、スマホ依存から脱却するための対策も存在します。
スマホの使用時間を制限し、運動を取り入れ、SNSデトックスを実践することで、スマホとの健康的な付き合い方が見えてきます。
本書を読むことで、スマホとの向き合い方を見直し、より充実した生活を送るためのヒントを得られるでしょう。