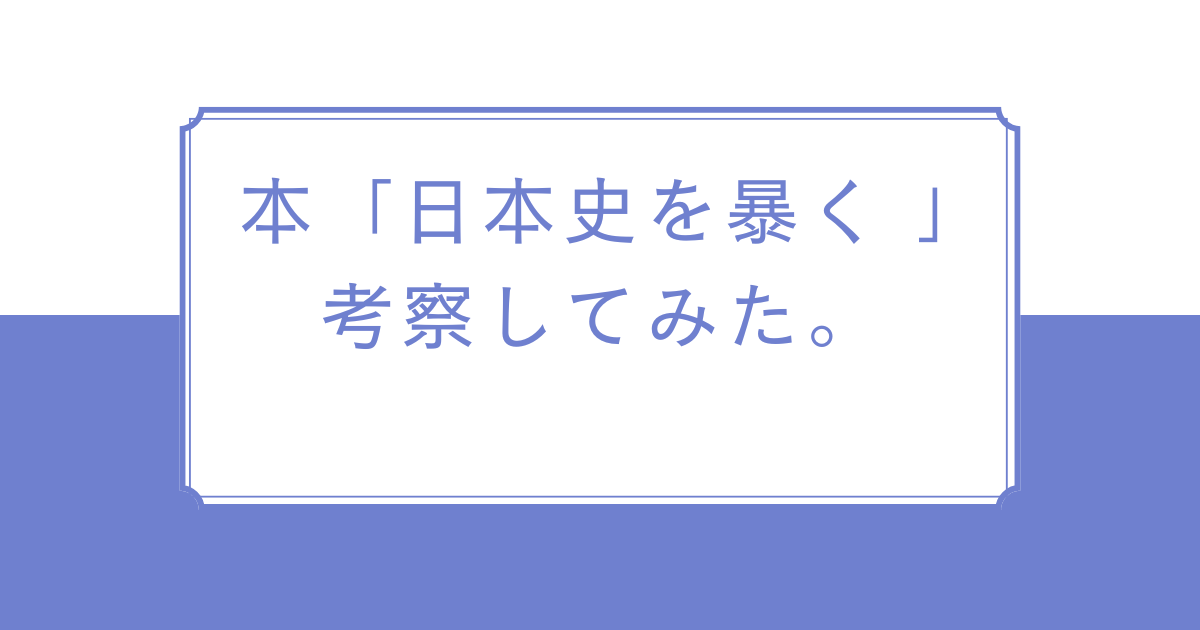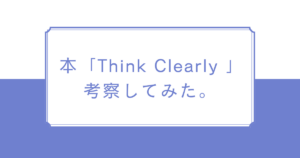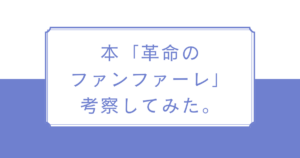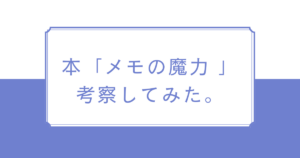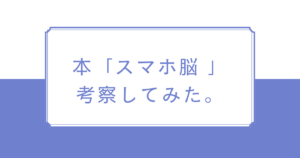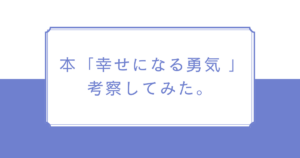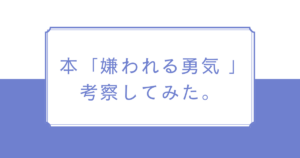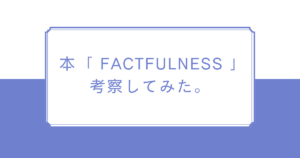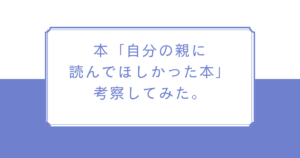磯田道史氏の著書『日本史を暴く』は、戦国時代から江戸時代に至るまでの日本史に新たな光を当てた興味深い作品です。
従来の歴史解釈に囚われず、文献や記録を基に当時の日本人の知識や価値観を掘り下げています。
以下では、本書の内容を3つの観点から考察し、その魅力をお伝えします。
考察① 信長が広めた地球球体説
織田信長が地球球体説を知り、それを広めたというエピソードは、本書の中でも非常に印象的な部分です。
信長は、宣教師フロイスから地球が球体であることを教わり、この知識を非常に興味深いものと捉えました。
その後、信長は自身の城の広間で講義を開き、多くの人に地球球体説を伝えました。
これには武将だけでなく、城の近くに住む子どもたちや一般の人々も含まれていたといいます。
さらには、襖を取り払ってまで大勢に話を聞かせるよう手配したことから、信長がこの知識をいかに面白いものと考え、広めたかったかがうかがえます。
また、信長がこの知識を広めた背景には、当時の宗教的価値観からの脱却を図る意図もあった可能性があります。
仏教勢力に対抗し、合理的で科学的な考え方を普及させようとした信長の姿勢が、このエピソードに色濃く表れています。
考察② 日本における宇宙論ブーム
信長の地球球体説普及がきっかけとなり、日本では宇宙論が広がりました。
戦国時代から江戸時代にかけて、このような科学的知識は社会に浸透し、特に知識人の間で大きな関心を集めました。
具体的には、イエズス会が宇宙論の専門家であるゴメスという宣教師を日本に派遣したことが挙げられます。
ゴメスは日本で宇宙論を教えただけでなく、後に『天球論』という専門書を出版しました。
この書籍は翻訳され、日本でも多くの人々に読まれることになりました。
江戸時代の後期になると、知識人の間で地球が太陽の周りを回っていることが当たり前の知識として定着しました。
さらには、「他の星にも空気があるならば、生物や人間がいても不思議ではない」というような考えが広まっていたことが、当時の日記にも記録されています。
このように、日本における宇宙論の進展は、信長を起点とした知識の普及が引き金となったと言えるでしょう。
考察③ 歴史の再発見と意外な視点
本書の魅力は、歴史に対する磯田氏の斬新なアプローチにあります。
単に既存の歴史事実を並べるのではなく、当時の記録や文献を綿密に調査し、新たな事実や意外な視点を引き出しています。
たとえば、大阪の金貸しの番頭が残した日記には、宇宙に生物が存在する可能性について考えた記述があります。
これにより、江戸時代の知識人が非常に先進的な思考を持っていたことが明らかになりました。
また、ヨーロッパでは地動説が激しい抵抗に遭っていたのに対し、日本では地動説が合理的で面白いものとして受け入れられていた点も、本書で掘り下げられた重要なテーマです。
このような発見は、日本人が当時どのように世界を見ていたのか、そしてどのように科学を取り入れたのかを再評価するきっかけとなります。
歴史を新たな視点から見ることで、従来の固定観念を覆す可能性を感じさせる点が本書の最大の特徴です。
まとめ
『日本史を暴く』は、従来の歴史観を再考する貴重な一冊です。
信長が地球球体説を広めたエピソードをはじめ、日本における宇宙論の普及、さらに当時の知識人の先進的な考え方など、驚きと発見に満ちた内容となっています。
磯田道史氏の綿密な調査と鋭い視点により、歴史の新たな側面が鮮やかに描かれています。
本書は、歴史ファンはもちろん、科学や文化に興味を持つすべての人にとって、知的好奇心を刺激する一冊と言えるでしょう。