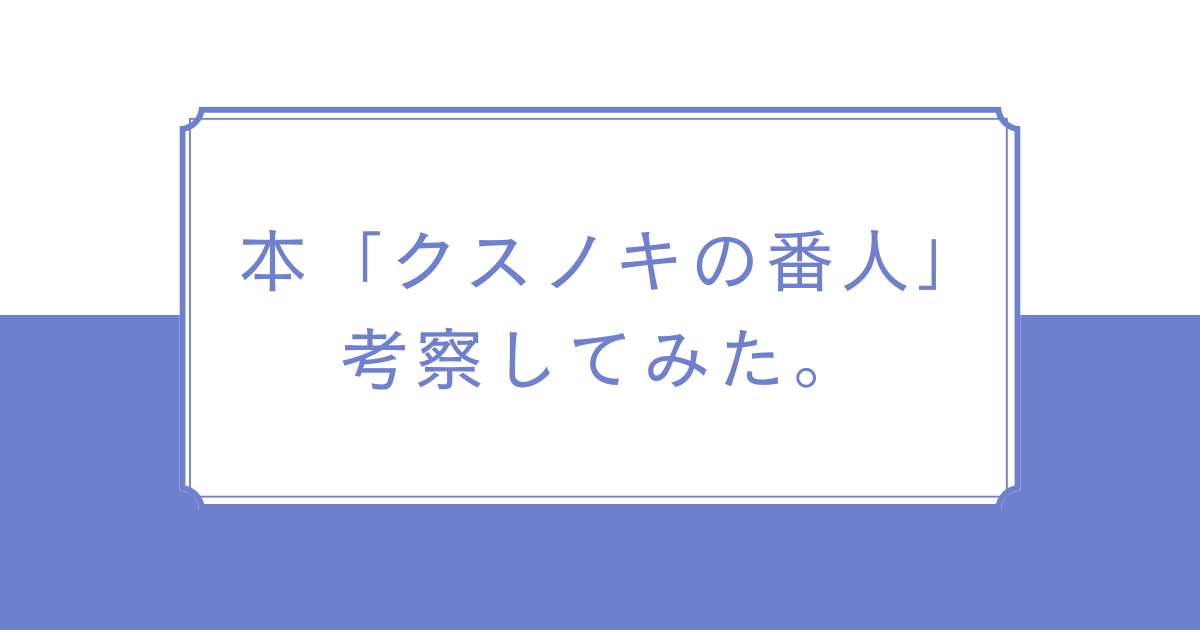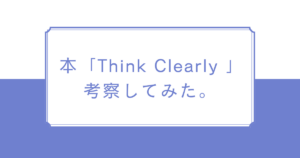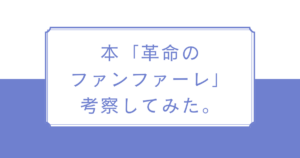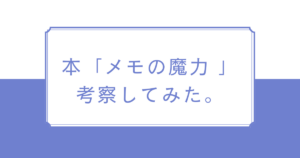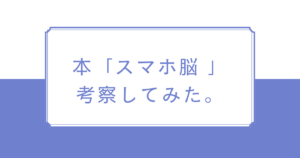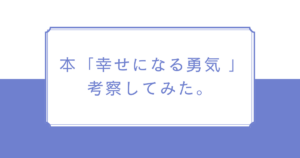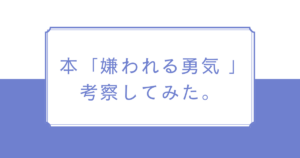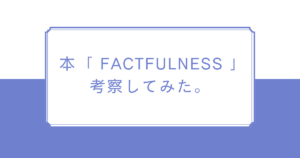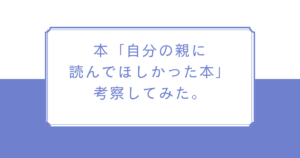東野圭吾の『クスノキの番人』は、ミステリー作家としての彼の印象を覆す温かなファンタジー小説です。
職を失った青年が「クスノキの番人」という役割を通じて成長し、訪れる人々との交流から「想いを伝える」ことの大切さを学びます。
物語は、不思議な設定と現実的な感情が絶妙に融合し、読者を深い感動へと導きます。
本記事では、この作品のテーマやキャラクター、そして人生における重要なメッセージについて考察を深めていきます。
考察① 「想いを伝える」ことの難しさと大切さ
東野圭吾が描く『クスノキの番人』は、「想いを伝える」ことの難しさをテーマの一つとしています。
物語の中で主人公の青年・レイは、仕事や自分自身に投げやりな態度を取る人物として登場します。
そんな彼が、訪れる人々の願いを受け止めながら、徐々に「想いを伝える」ことの大切さに気づいていきます。
特に、レイが自身を責める場面は、多くの読者に共感を呼ぶものです。
自分の想いを正直に伝えることは時に難しく、恐れや不安がその妨げとなるからです。
しかし、物語を通じて彼が成長し、自分自身と向き合いながら周囲の人々に心を開く姿は、読者にも勇気を与えます。
本作は、現代社会で多くの人が抱える「他者とのコミュニケーションの難しさ」に焦点を当てています。
その解決のヒントが、この物語の中に散りばめられているように感じられます。
考察② 主人公の成長と新たな役割
主人公のレイは、初めはやる気のない青年として描かれています。
しかし、「クスノキの番人」という新たな役割を通じて、彼の人生は大きく変わります。
訪れる人々の願いを聞き、その背景にある思いや悩みを知る中で、レイ自身も成長していきます。
この成長は、一連の出会いや経験がもたらしたものです。
例えば、訪問者が抱える問題に向き合う場面では、レイの考え方や態度に変化が生じていきます。
また、物語の後半で描かれる彼自身の過去と向き合う姿は、読者に深い感動を与えます。
この作品は、人間が新しい役割や環境に身を置くことで変わる可能性を示しています。
「成長」とは他者との関わりを通じてこそ起こるものだというメッセージが、この物語には込められています。
考察③ クスノキと「願い」の象徴性
『クスノキの番人』におけるクスノキは、単なる舞台装置ではなく、重要な象徴として機能しています。
願いを叶える力があるとされるクスノキは、訪れる人々にとって希望の象徴でもあります。
一方で、願いを叶える際のルールや制約は、簡単に手に入るものは真の幸福ではないことを暗示しているようにも感じられます。
また、クスノキを守る「番人」という役割は、人々の願いをただ受け入れるだけでなく、その願いに対して責任を持つ立場です。
レイが番人としての役目を果たす中で、クスノキが単なる願望実現の道具ではなく、人生の意味を考えさせる存在として描かれていることがわかります。
この象徴的なクスノキは、読者に対して「願いを叶えること」そのものの価値を問いかけています。
それは、自分自身の在り方を見つめ直す機会を与えるものでもあります。
まとめ
『クスノキの番人』は、想いを伝えることの重要性、主人公の成長、そしてクスノキという象徴的な存在を通じて、読者に多くのメッセージを伝える作品です。
一見シンプルなファンタジーのようでありながら、現代社会で生きる私たちに必要なヒントが随所に散りばめられています。
レイの変化を追うことで、自分自身のコミュニケーションや生き方について考えるきっかけを得られるでしょう。
また、クスノキという不思議な存在が私たちに問いかける「本当の願い」とは何か、というテーマにも心を揺さぶられます。
本作を通じて、自分や他者との関わりを見つめ直し、少しでも優しく、温かい気持ちを持てるようになることを願っています。
ぜひ手に取って、物語の中に込められた深いメッセージを感じてみてください。