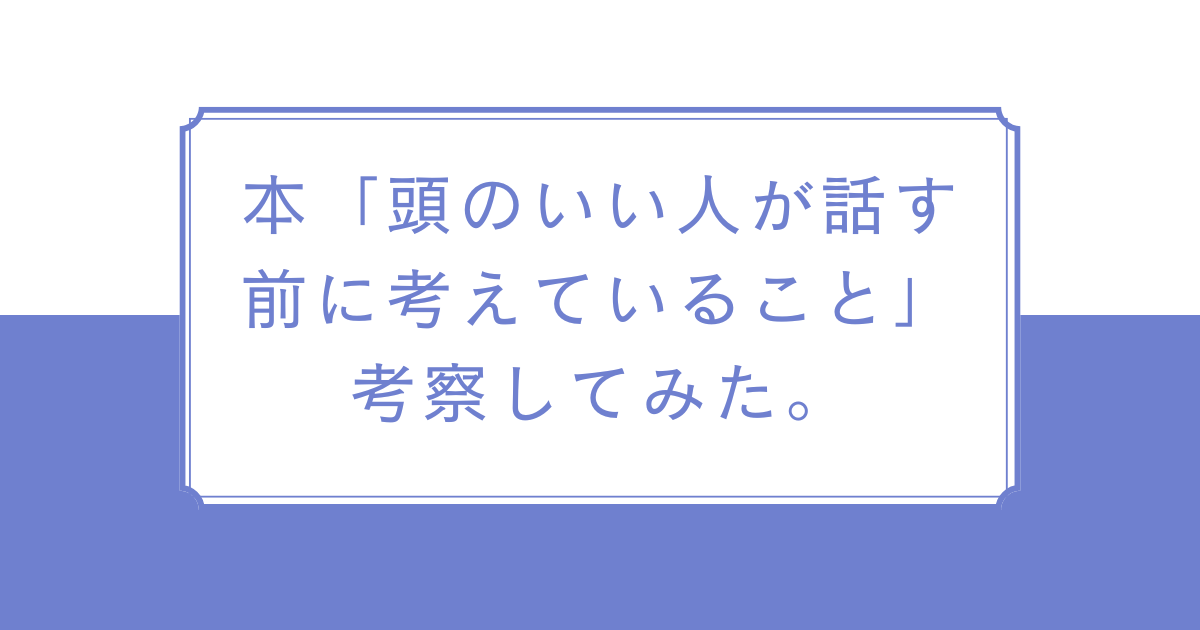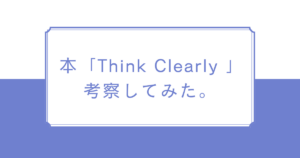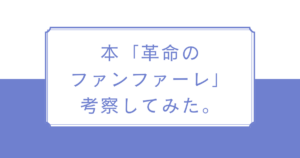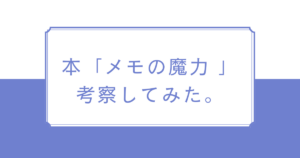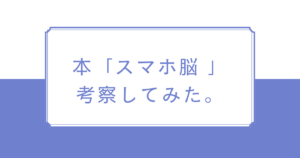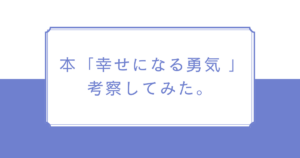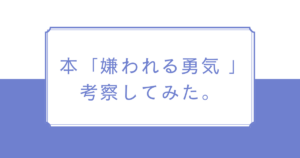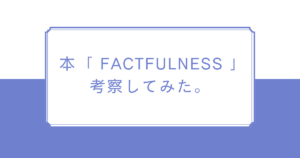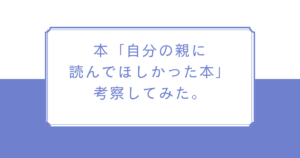「頭のいい人が話す前に考えていること」は、日常生活や仕事の中で「何を言うか」を再計算することの重要性を提唱した作品です。
言葉を使うために想考と指針を磨くことの重要性を細かく描いた一冊といえるでしょう。
以下では、本作の要点を「考察」の視点からまとめます。
考察①「とにかく反応しない」の重要性
「頭のいい人」の特徴の一つに、無関心に反応せず、感情を短治する能力があります。 本作では「ストレス時には痛りがちな決断に気をつける」ことが提唱され、読者に積極的な反省を促します。
例えば、怒りを解けずに返してしまったことが原因で、後で後悔した例は何度もあります。
そのため、何か言う前に「反応するための時間を作り」、人間の「早い思考」と「遅い思考」のバランスを執拗する手法が詳しく説明されています。
例として、怒りで感情的になりがちな人でも、積極的に定期的な試行を重ねることで、出来事を再構築するスキルを磨けるのです。
考察②「知識を他人のために使う」思考法
「頭のいい人」の中では、知識を示するのは自己への移し替えに活用されるのではなく、「相手に有益な手段」としての気配が必要です。
これは、コミュニケーションや他人の需要を警視し、「有益な情報」をとりいれるためのスキルを持つことを重要視するアプローチです。
コーヒーの例を使った説明では、個人の興味や問題に基づき、情報を財産の一部として求める形式が訴えられています。
これは、その場に定義されるだけでなく、お互いの認識を高める、最も効果的な意識となりえるのです。
考察③「解析と決断」の進め方
いくつもの話で「分析」と「決断」の大切さと、それを読者に対して調和する重要性が提唱されています。
例えば、簡単に見える情報の中に隠されたパターンを見出し、それを分類してメインテーマを求める能力です。
「最初に結論」を示された個人は、大抵の場合で問題の本質を重要視し、以降の解説について評価を行います。
「分析」と「決断」を相互に実践し、これに基づいた変化のまとめ方が詳しく描かれているのは、その実践の初期経験を最大化するスキルです。
また、話の全体像を把握し、余計な情報を取り除くことで、よりクリアな伝え方ができるとされています。
この「整理の力」が、頭のいい人の分かりやすさの根底にあるものと示されています。
まとめ
「頭のいい人が話す前に考えていること」は、積極的な思考と実践を高めるというテーマを根底から刺激する作品です。
何を言うかを話す前に精査し、想像力を駆使するための核心を教えられるのは、現代社会の調和力を大きく改善する助けとなるでしょう。
さらに本書は、思考の整理やコミュニケーションの改善を図る具体的な方法論を示し、個人のスキルアップだけでなく、対人関係の質を向上させるための実践的な知識を提供しています。
本書を通じて、より良いコミュニケーションと効果的な思考方法を身につける一助となるでしょう。