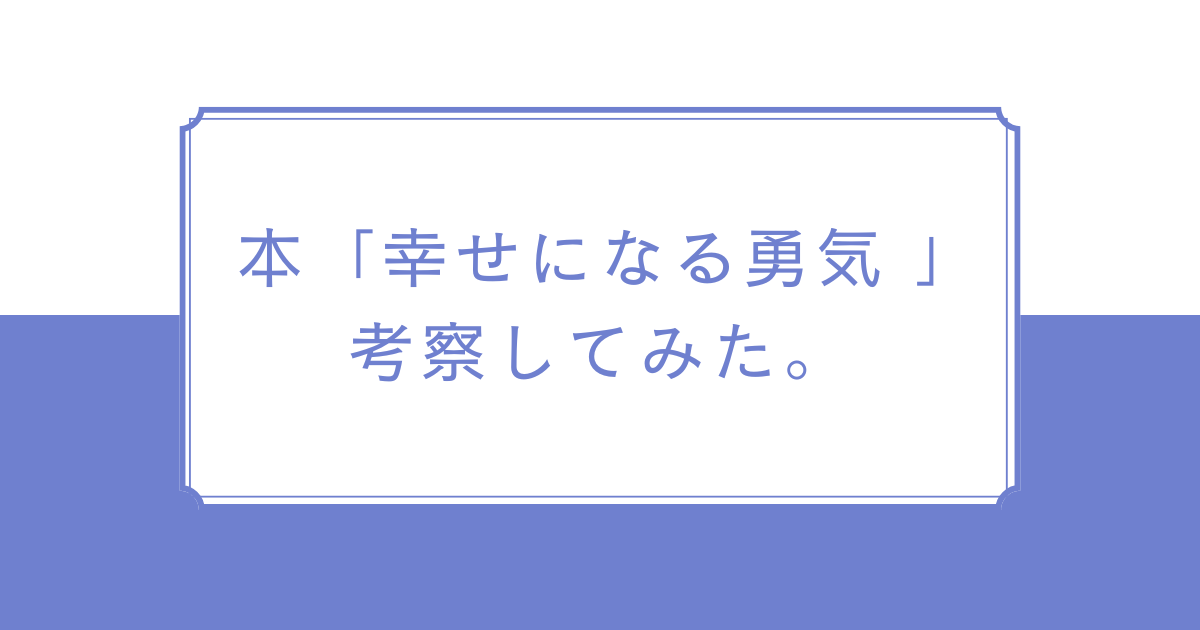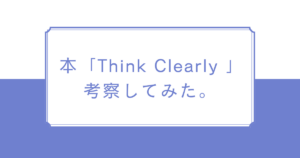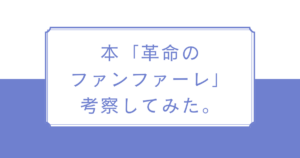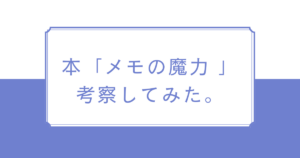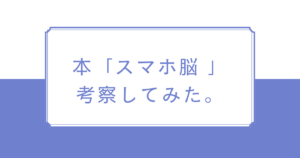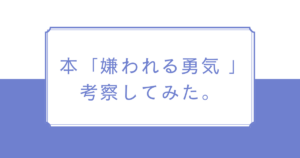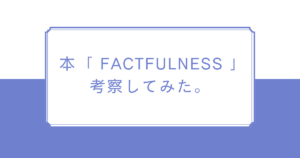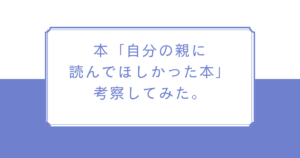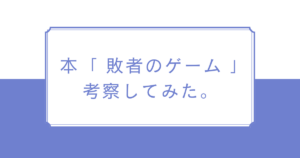「幸せになる勇気」は、アドラー心理学をベースにしたベストセラー「嫌われる勇気」の続編です。
前作と同じく、岸見一郎氏と古賀史健氏の共著で、人間関係や自己啓発に悩む人々に向けたメッセージが詰まっています。
本記事では、3つの考察から深掘りし、本書が私たちの人生にどのような影響を与えるかを探ります。
考察① 変われない本当の理由
アドラー心理学では、「人は変われる」という前提が根底にあります。
しかし、多くの人が「変わりたい」と思いながら、実際には変わることができません。
その理由は、過去の原因に縛られているからではなく、現在の目的に沿って行動しているからです。
例えば、「家庭環境が悪かったから暗い性格になった」と語る人がいます。
アドラー心理学では、これは過去を言い訳にしているに過ぎないと考えます。
本当は、他者と関わることで傷つきたくないという目的があり、その目的を叶えるために暗い性格を選んでいるのです。
変わりたいと思うなら、過去の原因に縛られるのではなく、今の目的に焦点を当てることが大切です。
考察② 問題行動の5つの段階
アドラー心理学では、問題行動には5つの段階があるとされています。
第1段階は「褒められたい欲求」で、親や教師に認められようとします。例えば、カンニングや偽装工作がこれに当たります。
第2段階は「注目獲得」で、目立つことで特別な存在になろうとします。いたずらや騒ぎを起こすことで注目を集めます。
第3段階は「権力争い」で、誰にも従わず挑発を繰り返します。親や教師を挑発し、戦いを挑むような行動が見られます。
第4段階は「復讐」で、愛の欲求が憎しみに変わり、相手を困らせる行動を取ります。ストーカー行為や引きこもりが典型的な例です。
第5段階は「無能の証明」で、自分はダメだと信じ込み、諦めてしまいます。最初からできないと思い込むことで、問題行動を正当化します。
これらの問題行動は、隠された目的に注目することで理解できます。
例えば、子どもがカンニングをするのは褒められたいという欲求からであり、万引きや喫煙は権力争いの一環として現れることがあります。
教育者や親は、これらの段階を理解し、根本的な目的に目を向けることが重要です。
無意味な反省文を書かせるのではなく、問題の本質にアプローチすることが解決の鍵となります。
考察③ 自己成長と他者貢献
アドラー心理学では、自己成長と他者貢献は密接に関連しているとされています。
自己成長を追求することで、他者に与えられるものも増え、結果として他者貢献ができるようになります。
例えば、弓矢を作る名人がいる場合、彼は弓矢を作ることに専念することで、狩りの名人に貢献することができます。
このように、自分のためを追求することが、結果として他者のためにもなるのです。
重要なのは、自分がやったことが他者のためになっているという主観的な感覚を持つことです。
実際に他者が喜んでいるかどうかはわからなくても、自分が貢献していると思えることが幸せにつながります。
この主観的な感覚を持つことで、自己満足が他者貢献に繋がるという考え方は、アドラー心理学の大きな特徴です。
まとめ
「幸せになる勇気」は、アドラー心理学を通じて、私たちが抱える悩みの本質とその解決策を提示しています。
変わりたいと思うなら、過去の原因に縛られるのではなく、今の目的に焦点を当てることが大切です。
問題行動の5つの段階を理解し、適切な対応を取ることで、人間関係の悩みを解決することができます。
自己成長と他者貢献は密接に関連しており、自分のためを追求することが他者のためにもなるのです。
本書を読むことで、自分自身の生き方を見つめ直し、幸せになるための勇気を持つきっかけとなるでしょう。