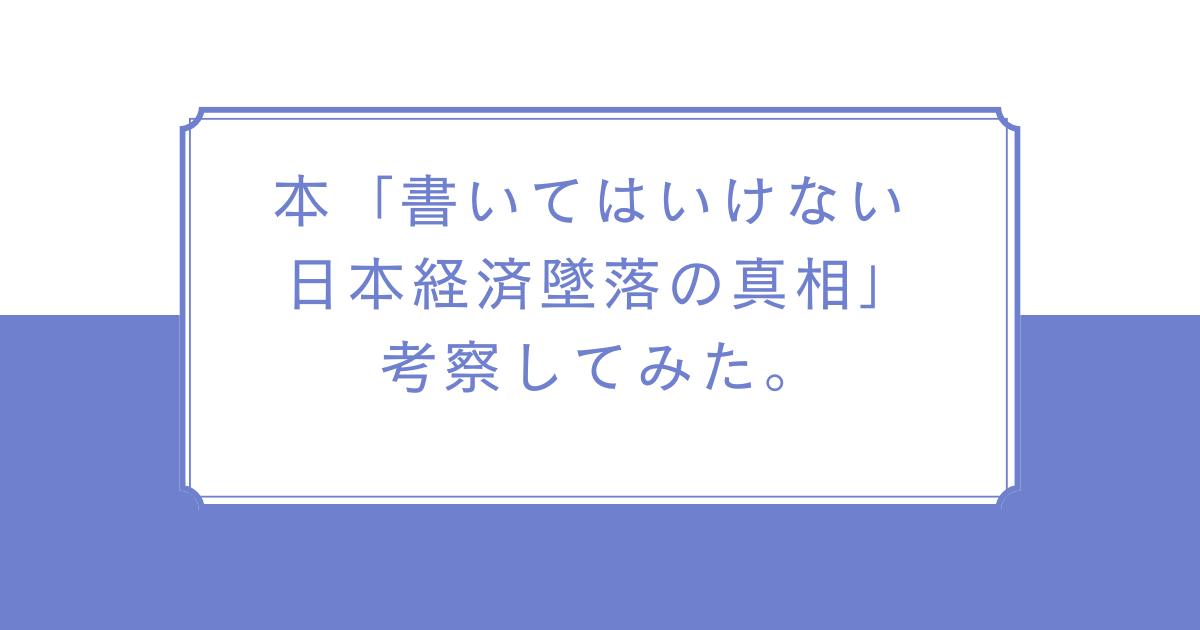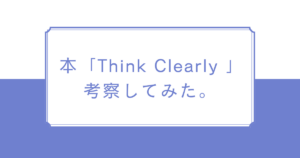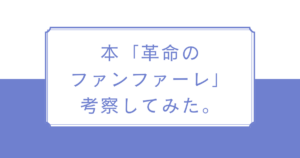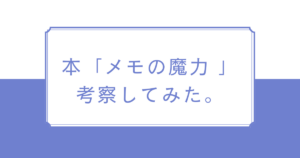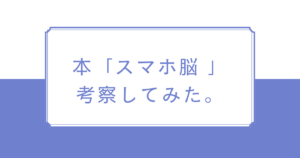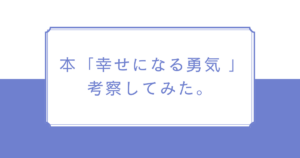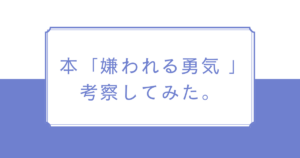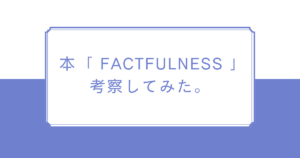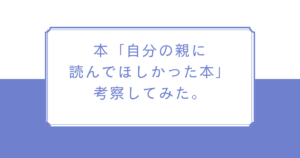森永卓郎氏の著書『書いてはいけない 日本経済墜落の真相』は、日本の経済政策の裏側に潜む複雑な問題を明らかにしつつも、希望を持たせる部分も多い作品です。
本書では、財務省やメディアの影響を受ける現状に警鐘を鳴らしながらも、改善の可能性や国民が変化を起こす力について強調しています。
以下では、著者が描く日本経済の課題とその解決のヒントについて、3つの視点から考察していきます。
考察①
本書の中心的なテーマは、財務省が日本の財政状況について国民をミスリードしているという点です。
日本は「借金大国」としてしばしば語られますが、著者はこのイメージが過剰に強調され、国民が必要以上に不安を感じていると指摘します。
実際、日本は1兆円以上の資産を保有しており、その財政状態は他国と比べて特段危険ではないとされています。
この点において、著者は国民が正しい情報を持つことの重要性を強調しており、知識を広めることで無用な恐怖を払拭できる可能性を示唆しています。
また、緊縮財政の見直しによって、経済が回復し得るという具体的なシミュレーション結果も紹介されており、日本がより良い未来を迎えるための具体的な道筋が描かれています。
考察②
著者はまた、メディアと財務省の関係性に深く切り込みますが、この部分においても単なる批判に終わらず、改善の可能性を示しています。
メディアが財務省の増税路線を批判しない背景には、「税務調査」というプレッシャーがあると指摘されていますが、これに対しても著者は解決の道を探ります。
メディアが正確な情報を発信し、国民がそれにアクセスすることで、政治や経済の透明性を高めることができるという信念が感じられます。
著者は、国民の声が集まり、正しい情報に基づく議論が行われることで、メディアもまたその本来の役割を取り戻すことができると提言しています。
結果として、情報が開かれた社会が実現すれば、財政政策もより国民の利益に寄り添ったものとなるでしょう。
考察③
本書は、日本航空123便墜落事故を例に、政府とメディアの隠蔽体質を厳しく批判していますが、この事例を通しても、希望の光を見出そうとしています。
過去に隠された事実を明らかにすることは、国民の信頼を取り戻す第一歩であり、透明な政府を構築するための鍵であると著者は訴えています。
また、著者が自身の経験を通して見出した問題点を率直に語ることで、読者にも変革への意欲を喚起しています。
このような歴史の真実を知ることで、国民がより自立した判断を下せるようになり、社会の透明性を高めることが可能となるでしょう。
著者は、日本社会がより公正で開かれたものへと進化するためには、国民一人一人の意識と行動が不可欠であるとしています。
まとめ
『書いてはいけない 日本経済墜落の真相』は、日本の経済政策や社会構造の問題点を鋭く指摘しながらも、同時に改善の可能性を探る視点が印象的な一冊です。
財務省による政策の見直しや、メディアの正確な情報発信の必要性を強調しつつ、読者に対して日本社会の変革に参加する重要性を訴えています。
また、過去の事件や隠蔽体質に対しても、その真相を明らかにすることで新たな社会の基盤を築ける可能性を示唆しています。
本書は、日本経済の課題を理解し、より良い未来を築くための重要な示唆を与える作品であり、読者に考えるきっかけを提供する一冊であると言えるでしょう。