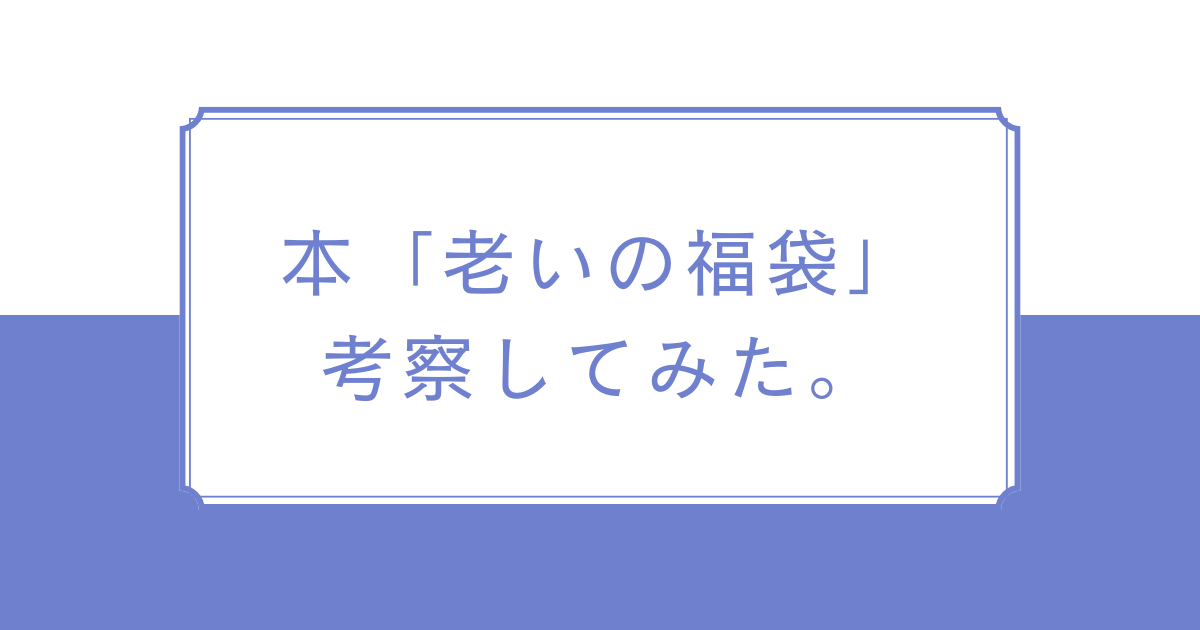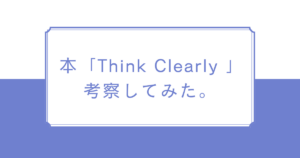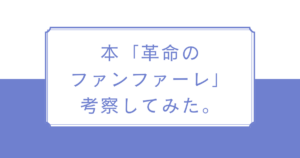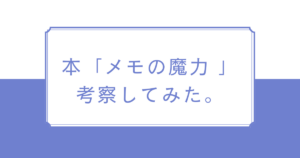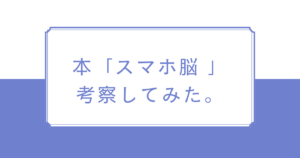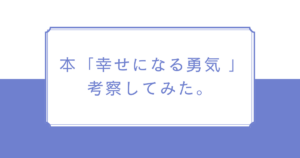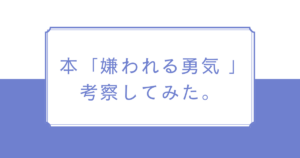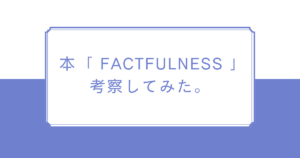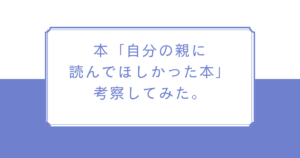樋口恵子氏の著書『老いの福袋』は、老いを生きることの喜びと困難を率直に描き出し、読者に深い共感を呼び起こす一冊です。
本書は、単なる高齢化社会のマニュアルにとどまらず、老いを多角的に捉え、より豊かな人生を送るためのヒントを与えてくれます。
本記事では、この『老いの福袋』を3つの視点から考察し、その魅力と深淵さを探求してみたいと思います。
考察① 老いを「ヨタヘロ期」と捉え直す
「ヨタヘロ期」というユニークな言葉は、老いをネガティブなイメージから解放し、より肯定的な視点で捉え直すことを可能にします。
著者は、この言葉を通して、老いを一つの過程として受け入れ、その中で自分らしく生きることの大切さを教えてくれます。
老いは誰しもが経験する普遍的な現象ですが、従来の社会では、老いは衰えや病の象徴として捉えられてきました。
しかし、樋口氏は、老いにも様々な可能性が秘められていることを示唆しています。
例えば、老後を新たな学びの機会と捉えたり、新たな人間関係を築いたり、自分自身の内面と向き合ったりするなど、老いならではの楽しみ方があることを教えてくれます。
考察② 老いを生き抜くための知恵
本書は、ヨタヘロ期をいかに生き抜くかための具体的な知恵も豊富に提供しています。
例えば、筋力トレーニングの重要性、社会とのつながりを維持することの大切さ、そして、心の持ち方など、多岐にわたるテーマが取り上げられています。
特に興味深いのは、著者が強調する「心の持ち方」の重要性です。
老いをネガティブに捉えるのではなく、残りの人生をどう生きるか、という視点に立つことの大切さを教えてくれます。
本書の教えを実践することで、読者はより健康で充実した老後を送ることができるでしょう。
また、本書では、具体的な事例を交えながら、老後を豊かに過ごすためのヒントが数多く紹介されています。
例えば、趣味を見つけること、ボランティア活動に参加すること、旅行を楽しむことなど、様々な選択肢が提示されています。
これらのヒントは、読者が自分にとっての「豊かな老後」を具体的にイメージする上で役立つでしょう。
考察③ 社会全体で考える「老い」
本書は、個人の問題にとどまらず、社会全体で考えるべき「老い」の問題についても深く掘り下げています。
例えば、介護保険制度の問題点や、高齢者の孤立問題など、社会的な課題についても言及しています。
樋口氏は、自身の経験や活動を通して、高齢者を取り巻く社会の現状を鋭く指摘しています。
本書を読むことで、読者は高齢者に対する理解を深め、より良い社会の実現に向けて貢献できるようになるでしょう。
高齢化社会が進む現代において、高齢者を取り巻く環境は大きく変化しています。
本書は、そのような社会の中で、高齢者がどのように生きていくべきか、という問いに対する一つの答えを示しています。
まとめ
『老いの福袋』は、老いをテーマにした数多くの書籍の中でも、特に実用的かつ共感度の高い一冊です。
本書は、老いに対する考え方や生き方を大きく変える可能性を秘めています。
老いを迎える人だけでなく、若年層や介護に関わる人々にとっても、必読の書と言えるでしょう。
本書を読むことで、読者は老いに対する新たな視点を得て、より豊かな人生を送るためのヒントを得ることができます。
また、高齢者を取り巻く社会問題に対する理解を深め、より良い社会の実現に向けて貢献できるようになるでしょう。
老いを迎えることは、人生の終わりではなく、新たな始まりです。 本書は、読者がその新たな章を豊かに生きるための羅針盤となるでしょう。