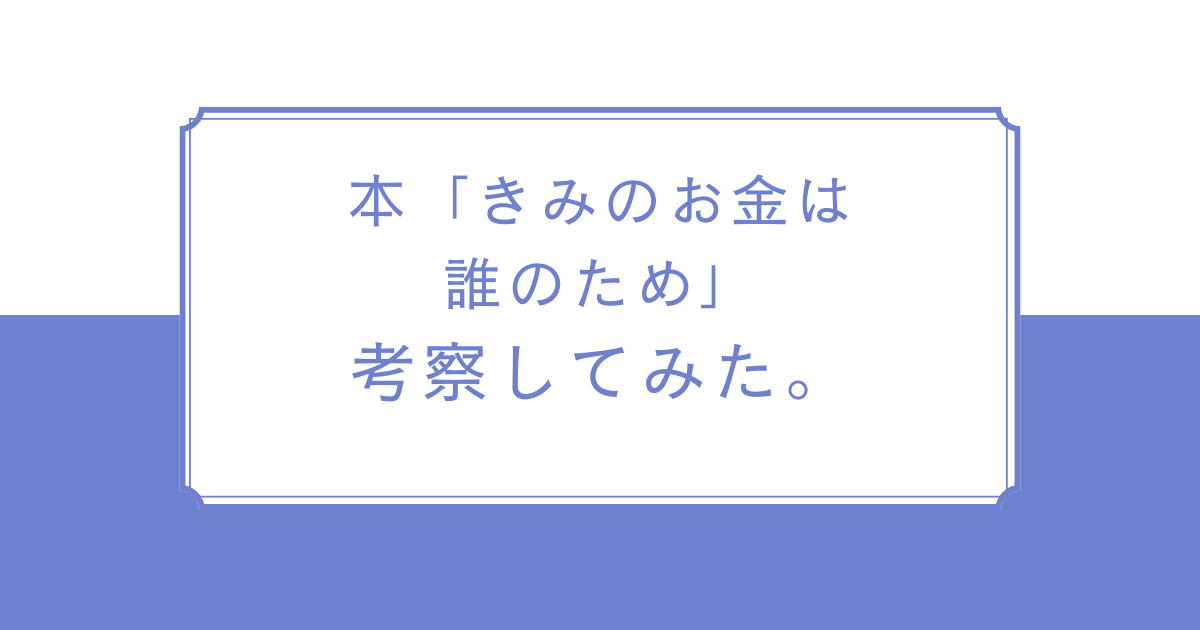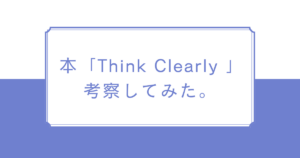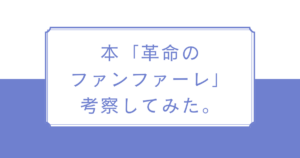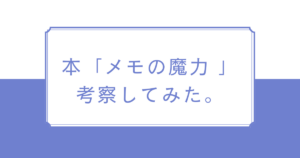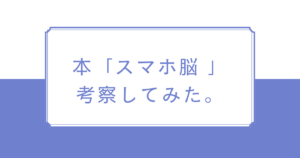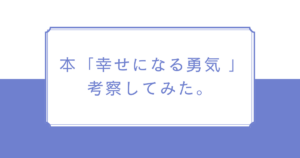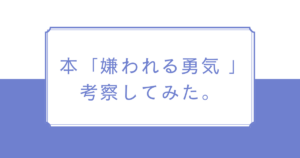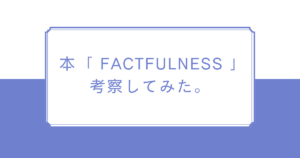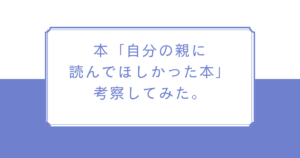田内学さんの『きみのお金は誰のため』は、お金の本質や社会の仕組みを小説形式でわかりやすく解説した作品です。
本書では、私たちの日常生活に密接に関わるお金の役割や限界を探りながら、社会全体を支える仕組みに焦点を当てています。
以下では、本書の重要なテーマを3つの視点から考察します。
考察① お金が解決する問題とその限界
お金は生活を支える重要なツールですが、全ての問題を解決できるわけではありません。
本書では、お金で問題が解決されるのは、他者がそのお金を受け取り、働いてくれる場合のみであることが強調されています。
例えば、スターバックスでコーヒーを注文するとき、お金が直接コーヒーを作るわけではありません。
お金を受け取ってコーヒーを準備する人がいるからこそ、商品として成り立つのです。
これは他のあらゆる場面にも当てはまり、家の修理や食品の購入でも同様の構造が見られます。
一方で、経済的な問題をお金だけで解決しようとするジンバブエの事例が取り上げられています。
同国では、ハイパーインフレが発生し、紙幣の価値が急落しました。
その背景には、生産力の不足を紙幣の発行で補おうとした政策の失敗がありました。
このように、お金が万能ではない現実を知ることが、本書の重要なメッセージの一つです。
考察② お金を貯めることの意義
お金を貯める行為は、多くの人にとって安心感を与えるものです。
しかし本書では、全体としてお金を貯めても問題の根本的な解決にはならないという視点が示されています。
例として、お正月に保存食としておせち料理を準備する昔の習慣が挙げられています。
お正月には店が閉まっており、食料を購入できないために保存食が必要だったのです。
この状況では、お金を持っていても商品がなければ意味をなさないことがわかります。
さらに、少子化や生産性の低下による影響についても触れられています。
労働人口が減少し、生産力が落ちれば、いくらお金を貯めても物資が不足するため、将来の備えとしては不十分であると指摘されています。
むしろ、生産性を向上させるための投資や仕組み作りが求められるというメッセージが込められています。
考察③ 社会基盤と未来への投資
本書では、将来の豊かさを支えるのは、教育やインフラといった社会基盤の充実であると述べられています。
例えば、年金問題について考える場合、単に仕送りを増やすだけでは問題は解決しません。
生産性を高めるための教育改革や、効率的な医療システムの整備が必要不可欠です。
また、お金をどのように使うかが個人の選択に影響を与えることも示されています。
どの企業に投資するのか、どのような政治家を選ぶのかといった選択が、社会全体に影響を及ぼします。
一人ひとりの意識が、持続可能な社会を築くための原動力となるのです。
本書は、これらの視点を通じて、経済の仕組みと私たちの役割を再認識させる内容となっています。
まとめ
『きみのお金は誰のため』は、お金と社会の仕組みを考える上で、非常に示唆に富んだ一冊です。
お金が問題を解決する手段である一方、その限界や影響についても深く掘り下げられています。
また、将来の備えとしての社会基盤の重要性や、生産性向上への投資の必要性が具体的に示されています。
普段、経済について考える機会が少ない方でも、本書を通じて興味を持ち、理解を深めるきっかけになるでしょう。
ぜひ一読して、お金に対する新たな視点を得てみてください。